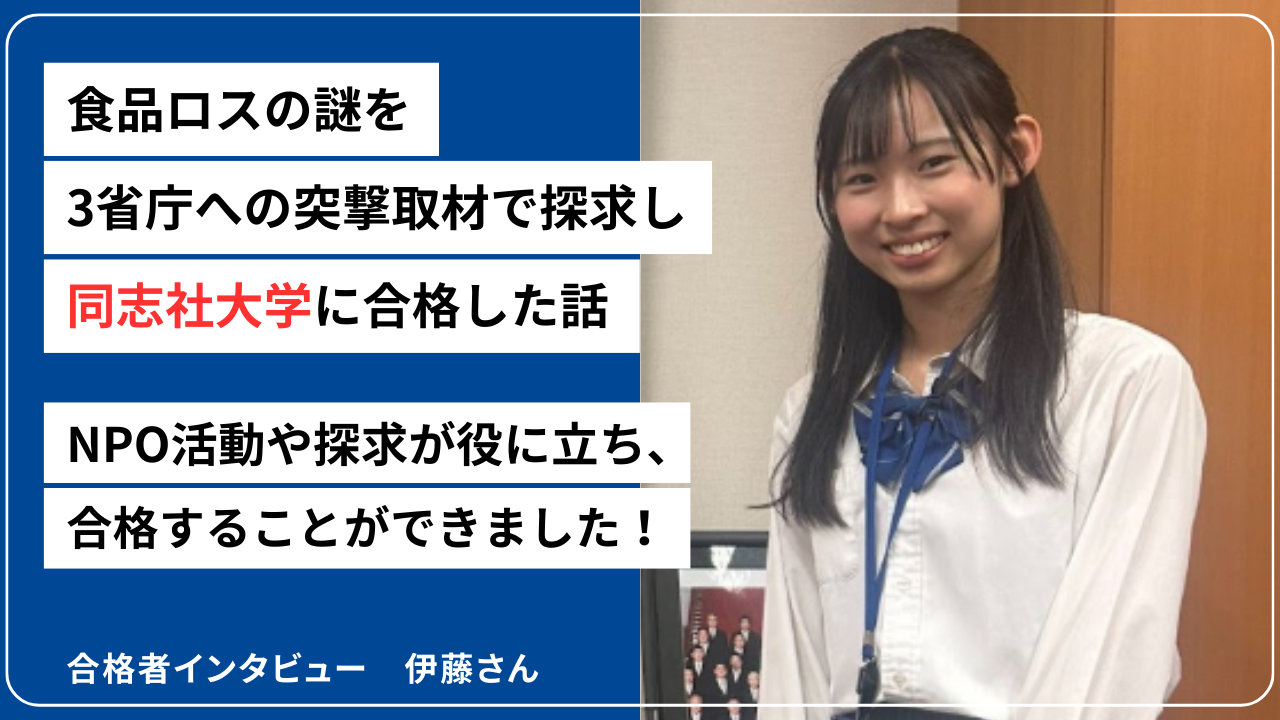食品ロス削減への問い。「伝わらない政策」を「人が動く情報」へ変えたい
「制度が整っていても、なぜ人の行動は変わらないのか」——同志社大学政策学部に合格した伊藤文さんが、高校2年生の食品ロス削減探究を通じて辿り着いた、根本的な問いです。生徒への意識調査、環境省・消費者庁・農林水産省への聞き取り調査、京都大学の研究者への面談、そしてNPOでのボランティア活動。複数の現場を行き来する中で、彼女が発見したのは、「制度やメディアそのものではなく、『伝え方』という、目に見えない課題」でした。その気づきが、やがて「メディアを通じた行動変容」という学問的テーマへと昇華し、同志社大学での本格的な探究へと導いたのです。

「無関心」との衝撃——若者の意識調査から始まった違和感
高校2年生の6月、伊藤さんが「食品ロス」をテーマに選んだきっかけは、シンプルでした。
「自分が食べることが好きで、食について触れたいと思ったから」
しかし、その後に実施した「生徒への意識調査」で、彼女は予想外の現実に直面します。
回答は「無関係だ」「SNSでは見かけない」——表面的で、浅かったのです。
「高校の生徒たちが、食品ロスという社会課題を『遠い話』として捉えていた。問題意識の希薄さに危機感を覚えた」
それは、単なる「若者の無知」ではなく、より深刻な問題を示唆していました。社会課題についての情報が「若者に届いていない」という現実だったのです。
その違和感が、彼女の探究の方向性を大きく変えました。
「食品ロスという課題そのものより、『なぜこの情報が届かないのか』という伝達の問題に没頭するようになった」
三つの現場での聞き取り調査——「制度の複雑さ」と「発信の断片化」
伊藤さんが次に向かったのは、食品ロス問題の「最前線」でした。
環境省・消費者庁・農林水産省の担当者へのインタビュー
そこで見えてきたのは、意外な現実でした。
「制度の複雑さと、縦割り行政による推進力の分散」
各省庁は独自の観点と役割を持ち、発信が「断片化」していた。多くの制度や支援策が存在するにもかかわらず、それらが生活者に届かず、実効性に乏しいのです。
そして、その問題を認識していたのは、何と各省庁の担当者自身だったのです。
「『制度があっても人の行動が変わらない』——その現実に直面した時、私は気づきました。これは制度設計の問題ではなく、『伝え方の問題』なのだと」
堀内詔子議員へのインタビュー
さらに彼女の理解を深めたのが、政治家への聞き取りでした。
堀内氏が語ったのは、家庭系食品ロスが減らない背景にある、「消費者の安全性への過度な要求」でした。
「賞味期限を見直す努力は制度的に進んでいるが、それだけでは行動は変わらない。制度と受け手の隔たりを埋める『伝え方』の難しさは、すでに生活者の中に深く根付いた前提を覆す大きな壁として存在していた」
つまり、問題は「制度」ではなく、「生活者の心の中に根付いた『前提』」だったのです。
理論的な視座をもたらした、京都大学の研究者との対話
伊藤さんが「無力感」に陥った時、それを理論的な視座へと変えてくれたのが、京都大学地球環境学堂の浅利准教授との対話でした。
「メディアには行動変容そのものを促す力は限られている。しかし、パーソナルメディア——直接的な働きかけこそが強力な起点になる」
SNSやテレビは「社会の空気」を作ることはできる。しかし、実際に人を動かすのは、「身近な人との対話」なのだと。
さらに浅利氏は、発信者の責任を強調しました。
「伝える内容と伝わる内容の差の責任は発信者にあり、情報を受け取る人の『価値観や状況』に合わせた伝え方の設計が重要である」
その言葉が、伊藤さんの心に深く刻まれました。
「『人が動く情報』とは何か」
その問いが、彼女の新たな探究へと導きました。
ボランティア活動の中での、「パーソナルメディアの力」の実感
その問いに対して、彼女は一つの「手がかり」を、自分のボランティア活動の中に見つけました。
NPOと協力し、社員食堂で余った食品を回収して高齢者の方に届け、共に食卓を囲む活動。
そこで起こったのは、SNSでは決して起こらない、ある光景でした。
「食品を手にした高齢者の笑顔を見て、『食品ロスの削減は制度やキャンペーンではなく、人と人のつながりから生まれる』と実感した」
SNSでは得られない、信頼関係の中で、行動は確かに変わっていくのです。
浅利氏の言う「パーソナルメディア」の力を、自分自身の体験として感じた瞬間でした。
「違和感」から「仮説」へ——学問的テーマの形成
これらの探究と実践を通じて、伊藤さんの心の中に、一つの「仮説」が形成されました。
「制度が整っていても生活者の行動が変わらないのはなぜか、人を動かす伝え方とは何か」
その答えは、シンプルにして、深かったのです。
「『誰から・どう伝えられるか』という関係性の中にこそ、行動変容の鍵がある」
制度は必要だ。情報も必要だ。しかし、それだけでは不十分である。受け手の価値観や状況に寄り添う「媒介者の存在」が欠かせないのです。
しかし、彼女はその仮説があくまで「一つの視点に過ぎない」ことを認識していました。
「複雑に絡み合う要因の中で、どのようにすれば人が動くのか。その問いに対して明確な答えを導き出し、その方法を実践するためには、同志社大学政策学部での学びが必要不可欠である」
同志社大学政策学部での学び——理論と実践の統合
伊藤さんが同志社大学を選んだのは、「政策」と「メディア」と「社会」を同時に学べる環境だったからです。
社会調査法やメディア分析を通じた、人々の意識・行動の実態把握
データという客観的な視点から、「人がなぜ動かないのか」を分析する力。
メディア実践科目による、試行錯誤
「誰にどのように伝えれば行動につながるのか」という視点から、伝え方そのものを設計し、実践する機会。
砂川ゼミ・木村ゼミでの専門的な探究
制度と現場のギャップ、意識と行動のズレを、学問的に追究する場。
さらに、関礼子教授の「環境社会論」や、貞包英之教授の「消費社会論」といった授業を通じて、「消費という行為そのものの社会的意味」を問い直す機会も得られるのです。
最終的な目標——農林水産省での実践
伊藤さんの最終的な目標は、明確です。
「将来、農林水産省に入り、InstagramやTikTokなどのSNSを使い、食品ロスの現状や削減方法をわかりやすく伝え、『自分ごと』として意識してもらえるような広報活動をしたい」
しかし、その目標を実現するために、彼女が同志社大学で学ぶのは、決して「SNS運用のテクニック」ではありません。
それは、「なぜ人は動かないのか」という根本的な問いに、学問的・実践的にアプローチする力なのです。
情報と行動をつなぐコミュニケーション。制度と現場の橋渡し。そして、「パーソナルメディア」と「マスメディア」の有効な組み合わせ方。
それを、高校時代の探究で見つけた「違和感」を起点に、大学で理論化し、実践化する。
伊藤文さんの大学生活における最大の挑戦は、そこにあるのです。